オムライス
今、最も乗りに乗っている小説家、杉谷良一。
三十代半ばで脱サラし、ずっと夢だった小説家になるため、貯金を切り崩しながら執筆に励んだ日々が八年続いた。
そんな彼が半年前に発売した「真綿のゆりかご」は、口コミやSNSで話題となり、発売後数ヶ月で五十万部を突破、先日公開された実写映画も興行収入は三十億円は優に超えるだろうと予想されるほどの人気ぶりだ。
そんな彼は今、とある店の前に立っていた。
小説家しか入れないという小さな食堂。
お代はこれまでに書いた小説だけで、最高の料理が食えると言われている。
その店の名は「しのみや食堂」
首都郊外のニュータウン。
近代的な外観と色の家々が立ち並び、そのほとんどには一台数千万円する高級車が置かれている。そんな高級住宅街を歩くこと十分。大きな家の間で申し訳なさそうにしている小さな民家があった。
それが「しのみや食堂」だった。
ぴんぽーん、とふぬけた音のチャイムが平日昼の住宅街に響く。良一の周りに人はおろか、犬や鳥の気配すら感じず、少し不気味さを覚える。
ほどなくして玄関のとびらが開いた。濡れた黒髪をひとつにまとめ、ベージュのタートルネックに落ち着いたネイビーブルーのエプロンをつけた美しい女性が現れた。
全体的な美しさはもちろん、白く透き通った肌と、どことなく切なそうな未亡人風の表情、なにより月のように輝く黄色い瞳に、良一は心を奪われた。
「いらっしゃいませ。杉谷様ですね、お待ちしておりました」
女性は良一を見るなり、低く落ち着いた、まるで男を聞き間違うような声で……
「え……男?」
「はい。店主の篠宮ひかると申します」
……女の人じゃなかったのか…。
このご時世見た目や性別に言及したりするのはよくないのはわかっているし、仮に女性だったとしても何もしないが、ほんの少しだけショックを受けた。
良一がこの店にきた理由は、いわゆる燃えつき症候群が原因だった。
これまで八年間、小説家になることだけを考えて、雨の日も風の日も、胃腸炎で救急車に運ばれたときも毎日本気で小説を書いてきた。今ではその努力が実り、SNSや口コミではいろんな人に賞賛され、いろんなところで「先生」と呼ばれるようになって、満足するようになってしまった。
ある日出演したテレビの司会者に、「次はどんな話を書かれるんですか?」と聞かれたとき、何も答えられなかったのが悔しかった。今まで小説家になったら、いろんなテーマの物語を書いて書いて、書きまくろうと思っていたのに、このザマなんて情けない。
なんとか打開するため、いい方法はないか仲良くなった作家に聞いたところ、しのみや食堂を勧められたのだった。
「……はあ」
店の中で大きくため息をついた。
店というにはあまりに小さく、殺風景すぎる。
この部屋にあるのは、二人用の小さな木製テーブルと、セットになっている木製の椅子。テーブルの真上からつるされている照明器具は小さく、ほんのりとしか光らないため、全体的に暗い。壊れているのかもしれない。装飾品は一つもなく、南側の大きな窓から小さな庭を見渡せるものの、小さな細い木が弱々しく立っているだけ。他の家が陰になって、日差しもない。そんなところにBGMなんてあるはずもなく、どこかの部屋でひかるが料理している音がかすかに聞こえるだけだ。
もうこれは部屋と言うより独房といった方が正しいかもしれない。
「ダメだ。ここにいたら気分が沈む」
お手洗いにでも行って気分を変えてこようと部屋を出たが、廊下も殺風景で薄暗い。自分の家も装飾品はないし暗いが、得もいわれぬ不穏な空気がここには流れていた。
最初ひかるに言われたとおり、部屋を出てすぐ右側のドアを開ける。
ガチャンー
鍵がかかっているようだ。ひかるが入っているんだろうか。でも近くで食材を炒める音がする。
じゃあいったい誰が……?
背中を冷たい汗が走った。実は本当の店主がいて、閉じ込められているんではないか?もしくは俺を殺そうと別の誰かがひそんでいるんでは……。そもそもここに店なんてなくて、人の姿をした化け物が俺を食べようとしているんじゃ……。
「杉谷様」
低い声。すぐ後ろにいるんだろう、圧を体中で感じる。体中から汗が吹き出て、鉛のように固まってしまい、振り向くことができない。
今まで小説家になるために頑張ってきたのに、こんなところで終わるのかよ!もっといろんな話を書きたかった、自分の可能性を試したかったのに!
俺の人生もここまでか……!
「お手洗いはとなりの扉ですよ」
背後のひかるがとなりの扉を開ける。ごくふつうのトイレが見えた。
「……あれ…?」
「ここは洗面所ですよ」
ひかるの長く細い腕が、目の前の扉を開ける。
確かに洗面所のようだ。白基調の洗面台と、床に山のように積みあがった洗濯物が見える。
「あっ、ごめんなさい。お見苦しい物をお見せしました……」
緊張が解けてひかるのほうへ振り返ると、顔が少し赤くなっていた。
「あ、えっと、それで……お食事の準備ができました。お部屋に戻りましたらお出ししますね」
「……はい」
今まで不思議なオーラを纏っていたひかるが、とたんにどこにでもいる人間に見えた。俺はいったい何を見ていたんだろうか。何を考えていたんだろうか。
どっと疲れた己の体をトイレに押し込んだ。
「お待たせいたしました。ご注文いただいたオムライスと付け合わせのサラダ、ポトフでございます。ごゆっくりお楽しみください」
ひかるは並べた料理の説明をすると、そそくさと部屋を出ていった。
壊れていると思っていた照明に程良く照らされ、料理がキラキラと輝いている。それだけで部屋の中が明るくなった気がした。良一が注文していたのは薄焼き卵が乗った庶民派オムライスだった。たまごの上に、ケチャップがまんべんなく波状にかけられている。お袋の味でもなんでもないが、たまに無性に食べたくなるのだ。
オムライスの真ん中にスプーンを入れる。
ケチャップライスのほんのり酸味のある香りが一気に広がる。そのまま口へ。
甘めの卵焼きにコクの効いたケチャップライスがよく合う。柔らかいご飯に具材の鶏肉とタマネギがアクセントをくれる。しゃきしゃきすぎでも、くたくたすぎでもない絶妙なバランスのタマネギと、柔らかい食間にハリをくれる鶏肉。ひとくち食べれば食べるほどうまさが広がる。
ポトフにも手をつける。ニンジン、ジャガイモ、レタス、それにソーセージが入っている。これがまずい訳がない。スープを一口飲む。
「…ああ、この味だよな」
味付け調味料の味だけでも、ただのお湯でもない。正真正銘のポトフの味がする。ソーセージのうまみだけでなく、素朴なあたたかい野菜たちの味がしっかりとわかる。途中でサラダを食べて口の中をリセット。そしてまたオムライス、ポトフと食べていく。
オムライスを食べている途中、無意識のうちにスプーンでたまごをめくっていることに気が付いた。大学時代、学食のおばちゃんにオムライスの端にグリーンピースを山盛り入れられていたからだ。
あれをみつけては何度もクレームを入れ
「そんな年にもなってグリーンピースが食べられないなんて恥ずかしくないの!いいからちゃっちゃと食べなさい!」
と怒られていた。当時はなんでこんな横暴な奴が学食作ってるんだとか、早く辞めちまえとか文句を言っていた。大人になった今ではそういったおせっかいがどれほどありがたかったか身にしみる。
とはいえ良一はあのせいでまだグリーンピースを食べられないでいるが……。
ひかるが作ってくれたオムライスには、最後までグリーンピースは入っていなかった。当たり前だけど少し悲しい。
これくらいのご飯ならいつも食べているのに、いつもとは違う幸せな気持ちでいっぱいになった。これが「食べる」ってことなのかもしれない。暗かった庭に、ほんの少し日差しが差し込んでいた。
少し赤くなった空を見上げる。
後ろを振り向くとひかるが丁寧にお辞儀をしている。トイレにいったときは本当に怖かったなあ……。
でも、自分の小説に対する気持ちがよくわかった。確かに今は燃え尽きてはいるかもしれない。それでも、俺はやっぱり小説を書き続けたい。ネタも気力も、まだ何もないけど、少しずつまた歩き出せる気がした。
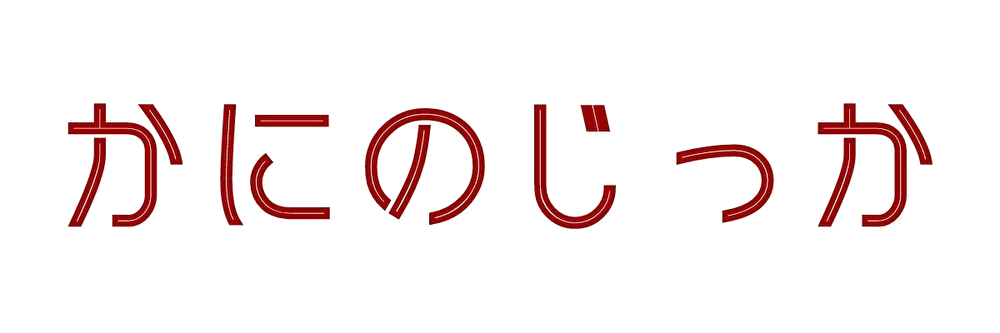

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます