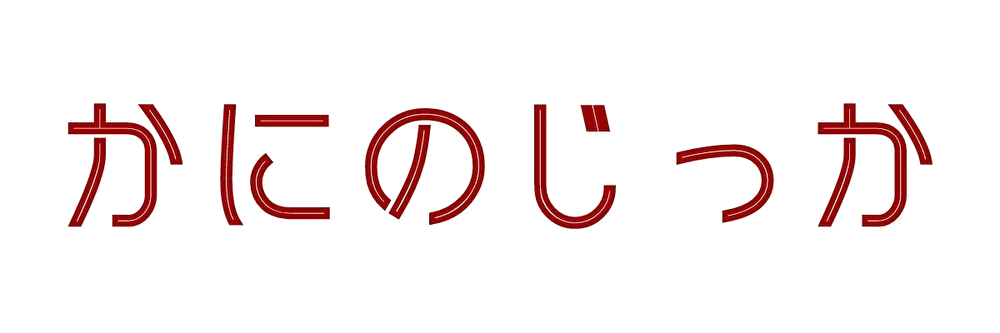ステーキ
その不思議な店は住宅街の中にあった。
富裕層向けだろうこの住宅街は、独特なデザインの大きな家がいくつも建ち並んでいる。そのすべてに外国産の車が最低でも二台は停まっており、家主の財力が並大抵でないことを物語っている。そんな町並みの中、大豪邸に囲まれて申し訳なさそうにしている小さな二階建ての家がその店だ。のれんも看板もない、ごくふつうの玄関をくぐれば、三つ星に引けを取らない極上の料理が楽しめる。
しかし、入るには条件がいる。
それは小説家であることと、お代の代わりに、今まで書いた小説を店主に渡すこと。
それが不思議な店「しのみや食堂」のルール
今日も一人、小説家が入っていく。
安藤道久は、深夜のしのみや食堂でひとりうなだれていた。
朝はきっちり着こなしていたであろうスーツはよれ、おしゃれながら清潔感もあるウェーブがかった黒髪も、今では汗で顔にぺったりと張り付き、顔は蒼白としており、目は生気を失っている。
六畳ほどの小さなリビングに、天井から小さな常夜灯が垂れ下がっている。
一人用の小さな木製テーブルと対になっているイス。ここにはそれしかない。南側の掃き出し窓の外には木が植えられているが、他の家に邪魔されて日当たりがよくないのかやせこけている。あまりに殺風景で、独房を感じさせるこの部屋が、より道久の心を重くさせた。
安藤道久はここ数年で小説を書き始めた新人小説家だ。学生時代からいろんな業種で働いてきた経験と知識をもとに、仕事に悩みながらも真剣に向き合い、前に進む人々を描く、いわゆるお仕事小説を専門にしている。SNSを通じて作品が広まり、初めての社会に悩む若者を中心に人気を博している。
今日は新しい小説のネタを探しに、山奥で活動しているという陶芸家のもとへ取材に出ていた。自分の作品を発信したいと悩んでいる陶芸家の元に、マーケティングを勉強している大学生が現れる。SNSでバズって一気に作品が売れたり、ちょっとした一言で炎上したり、いろんなことを経験して陶芸家として、一人の人間として成長する……。そんな話にする予定だった。自分もSNSで人気が出たから思い入れはかなり強い。絶対に成功させる気持ちでいた。しかし、道久が思っていたよりも陶芸は奥が深く、今の自分の力ではその世界をことばに、小説にすることができないと思い知らされた。そのあともショックのせいか下山中にスマホの充電がなくなったり、急いで乗った電車が反対方向のものだったり、一目惚れしかけた食堂の店主が男だったり……散々な目に遭っていた。
まさかこの自分がいち食堂の店主にうつつを抜かしてしまうとは……。
ここの店主である篠宮ひかるは、儚き未亡人と紹介されたら信じてしまいそうなほど美しい。濡れた長い黒髪をひとつにまとめて、落ち着いたベージュ色のエプロンは色気すら感じる。品のある眼鏡の奥には、吸い込まれそうなほど澄んだ黄色い瞳。道久の好みは快活な女性だが、あれをみて惚れない男はいないと思う。しかし一言ことばを発せば、落ち着いた男らしい重低音が響く。恋にも満たない気持ちは一瞬にして消えてしまった。少しでも鼻の下をのばしてしまった自分が恥ずかしい。
しかし、富裕層向けの住宅街に小さいながらもよく家が建てれたよな……。やっぱりプロの料理人だからお金を持ってるんだろうか、それとも愛人とかから出資されているのかもしれない。もしくは、そもそもこの店自体が幻で、明日になったら建物ごとなくなっていたりするのかもしれない。
ジュワァーッ
鉄板の焼ける音で目が覚めた。
変なことを考えている間に眠ってしまっていたらしい。体の疲れは少しもとれていないが、少しだけ頭がすっきりしている。
今回道久が注文したのは肉厚のステーキだった。いやなことが続いた今日は、やけ食いをしないと気が済まない。新人小説家といえど、もう三十六歳。少しずつ肉を食べるのが辛くなってきているが、今日は多少の無茶は許されるだろう。
コンコンと控えめなノックが鳴ったと同時にひかるが入ってきた。と同時に肉の匂いが部屋いっぱいに広がる。お盆の上にはジュージューと大きな音を立てている分厚いステーキの姿が。上品な手つきでテーブルに料理をおく姿に、思わず胸が高鳴ってしまう。
「お先にトマトとレタスのグリーンサラダと、オニオンスープです。ドレッシングはバルサミコ酢とオリーブオイルをかけてお楽しみください。……それとサーロインステーキです」
小さなテーブルにみずみずしいサラダと、黄金色のスープ、そしておおきな極厚ステーキが並んだ。みているだけで涎が止まらない。ひかるは足早に台所へ戻ってしまった。
写真を撮ろうとスマホを取り出そうとしたが、そういえば充電が切れたんだった。いや、こういう豪華な食事こそ、写真なんか撮らずにじっくり味わうべきだ。思い直して真っ先にステーキにナイフを入れる。切り込みから閉じ込められていた肉汁が一気に溢れ出す。すっと切り終わると、外は綺麗な焼き色で、中心にいくほどピンク色にグラデーションされている。テレビでしかみたことがない美しい焼き加減だ。切れ端からうっすらピンクの脂がしたたり落ちている。こんなの絶対にうまいに決まっている。
「あちっ」
口に入れたとたんにじゅわっと広がる肉汁。弾力があるものの柔らかい食感、噛めば噛むほど広がるうまみ。最高すぎる。すぐに次の切れ込みを入れる。またすぐに溢れる肉汁。すっきりとしながらも満足感のある脂、噛む度に喜びが増す肉の厚み!このうまさをなんと表現したらいいんだろう。語彙力のなさがイヤになるが、こんなのうまい以外の感想が必要だろうか。
ステーキの下にタマネギの薄切りがあった。肉をアツアツに保つためとか理由があるけど、肉汁をたくさん吸ってキラキラと輝いている。これもうまいに決まってる。……ほら!思わず笑いが出てくる。シャキシャキしすぎず、くたっとしていないちょうどいい歯ごたえだ。
脂に疲れてきたらサラダを食べる。こんなにみずみずしい野菜どこで手にはいるんだろう。ドレッシングのおかげもあって、口の中が一気にさっぱりする。スープも深い味わいで疲れ切った体が芯から温まるのを感じる。
その後も食べる手は止まらず、食べきれるか不安だった肉厚ステーキはあっという間になくなった。
「食った……」
残ったのは幸せな気持ちだけ。
帰ろうと席を立つと、台所へつながる扉が少し開いていた。隙間から、小説を読んでいるひかるの姿がみえる。大学時代、締め切りに間に合わなくて部誌に載せられなかった小説だ。今よりも破天候でつたないが、かなり気に入っている。ひかるの表情は儚いイメージとはうってかわって、宝の地図を見つけた少年のような生き生きとしていた。
「篠宮さんは、小説かかないんですか?」
とつぜん台所に入ってきた道久にひかるは目を丸くした。
「…さ、才能がありませんから……」
「そんなことないですよ!だってあんなうまい料理作れるんだもん。絶対面白いと思う。もし面白くなくても俺、絶対読むから」
「そうでしょうか」と小さくつぶやいたひかるは、少しだけ顔が赤かった。
店を出て伸びをした道久の体は、バキバキといやな音を立てた。明日は絶対に全身筋肉痛だろう。ここに来る前はあんなにいやだったのに、今ではこの痛みが勲章のように思える。ちらりと明日には消えているかもしれない店の方を振り向くと、大きく礼をした。