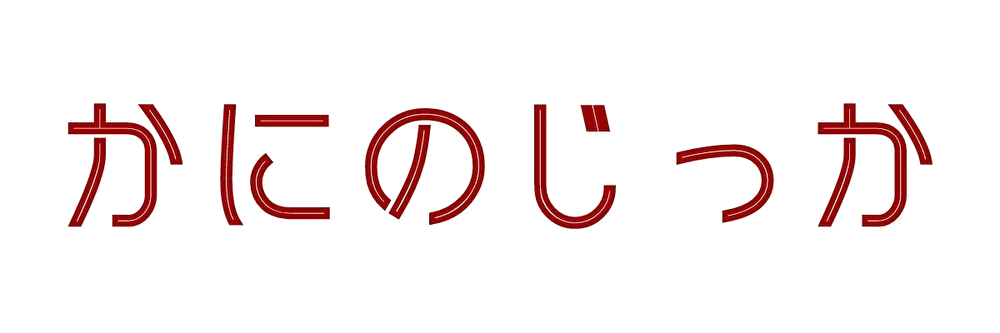担当編集者に言われたとき、梶田真由美は怒りよりもショックを覚えた。
三十代だがフレッシュさ溢れる男性編集者で、美しいとはほど遠い真由美に対しても満面の笑みで対応してくれる。毎度毎度ワンパターンな話の展開にも「大丈夫ですよ!今の時代だからこそ読まれるべきです」といつも笑顔で褒めてくれる。そんな彼の真顔が、心に深く刺さった。
それもそのはず、連載のボツが続いているのだ。このままいったら打ち切りになりかねない。ただでさえ売れていない真由美にとっては死活問題だ。
一階まで降りるエレベーターに、若い女性社員が入ってきた。ちらりとそちらを見ると、頭の先からつま先までおしゃれだし、バッチリ決まっている。なのにナチュラルで嫌味がない。ぼさぼさ頭に高校生のときから着ているよれよれのTシャツ姿の自分とはあまりに違いすぎて、心の中でため息をついた。
私もこんなに綺麗だったら彼もあんなに怒らないのかもしれない……。
若い社員を羨むが、かといって彼女のように身だしなみを整えようなど微塵も思わない自分のずぼらさにまたため息が出た。
「こういうときはあそこに行くしかない」
真由美はそう心に決め、エレベーターを降りた。
それは物静かな住宅街の中にある。
知らない人からただのお金持ちの家にしか見えない大きな一軒家、通称・しのみや食堂。
しかし入ることができるのは、一部の人間だけ。
その日の夜、真由美はどこかの家からただようカレーの匂いにお腹をすかせながらその家の前に立っていた。
チャイムを鳴らせば、ほどなくして木製のドアが開く。
満月のような優しく黄色い瞳に、腰まである長い黒髪、真由美よりも細く柔らかそうな体。
「お待ちしておりました」
そして、男性らしい低い声。家主の篠宮ひかるだ。
「こんばんは。まずはこれどうぞ」
真由美はひかるのギャップに臆することなく、お代であるUSBメモリを手渡した。とたんにひかるの目が子供のように輝く。
「今日ボツになった奴だけど」
「いつもありがとうございます」
高級料理店並の美味しいご飯を作ってくれる上に、お代はこれまで自分が書いてきた小説のみ。
そうここは小説家のみが入ることの許される秘密の食堂なのだ。
ずぼらで金欠の真由美にとって最高の場所で、以前から通っている。
今回真由美が頼んだのは、ほかほかのご飯に鳥そぼろと炒り卵、鮭のほぐし身が乗った三色丼だった。子供の頃大好きで、母に何度もわがままを言って作ってもらった思い出の一品。たまに無性に食べたくなるのだ。
部屋はダイニングキッチンとなっており、すぐ近くでひかるが鳥そぼろを作っている。
暇さえあればここに訪れているが、ひかるのことは依然として不明なままだ。見た目のギャップや、ミステリアスな雰囲気から「大文豪の愛人だ」とか「実は宇宙人だ」などと小説家らしい想像力豊かな噂が立っている。真由美からすればおいしいご飯が食べられるなら宇宙人でもかまわないが。
真由美はその間、プロットを組み直すでも今日の反省をするでもなく、目の前にある白い壁を無心で眺めていた。こういうところがダメなんだろうな、と思いつつも「しょうがない」ですませてしまう。
「お待たせしました」
ひかるが料理を持ってきた。
大きなどんぶりに、焦げ茶の鳥そぼろと黄色い炒り卵、ピンク色の鮭のほぐし身がバランスよく盛りつけられている。見た目は三色といえるほど鮮やかではないが、真由美の心を躍らせるには十分だった。
さらにきんぴらごぼうとわかめの味噌汁もつけてくれた。湯気が優しく立ちこめてはブラウンライトに消えていく。
「いただきます」
まずは三色それぞれを単体で楽しむのが真由美流、鳥そぼろと白米だけをすくって一口。一度噛んだだけでなくなりそうなほど柔らかく、噛めば噛むほど醤油と味噌の味が広がる。かといって鶏の味も負けていない。こんなの白米と合わないわけがない。そして炒り卵は、真由美の好きなしょっぱい味付けで、鮭のほぐし身は塩気がちょうどよく、鮭特有の味が口いっぱいに広がる。
それぞれを堪能した真由美は、鳥そぼろと炒り卵のあいだをすくい、さらに強引に鮭もすくって食べる。みんなそれぞれ味の主張はあるけど喧嘩しない、優しい味。母が作ったものとはけた違いでうまいのに、幼い頃の記憶が鮮明によみがえる。
好き嫌いが激しかった真由美の為に、ほうれんそうやグリーンピースなど野菜が盛りつけられた時は、「その手には乗らないぞ」と綺麗に野菜を残していた。それで、なんとしても食べさせたい母と絶対に食べたくない真由美で大喧嘩になる。
両親はまだ健在だが、会う度に身長が低くなっていて、親も老いるのだという現実を受け止められないでいる。
現実から目をそらすように味噌汁を一口すする。だしが何かとかは分からないけど、深い味がほんのりと胃を温めていく。思わず「はぁ……」と一息ついてしまう。日本人でよかった。
きんぴらごぼうに目をやる。コンビニやスーパーでちょくちょく買うことはあったが、こんなにも野菜がきらきらと輝いていただろうか。ごぼうとれんこんとにんじんがポリポリと心地の良い音を立てる。
ちゃんとした食事はいつぶりだろう。ここに来ても豪華な料理ばかり作ってもらっていたが、こんなに心の奥まで温まることはなかった。
「ごちそうさまでした。今日も美味しかったです」
「ありがとうございます」
ボツ原稿が面白くなかったのか、ひかるの目は申し訳なさそうにどこかを眺めている。
「……あの。何が編集者にウケるかよりも、何が書きたいか、だと思います」
「え?」
ひかるから話をかけられることがなかったので一瞬たじろいだが、どうやら真由美の原稿に乗せた魂胆はお見通しのようだった。
「すみません……。上から目線で……」
「いや全然……。うん、頑張ってみます」
弱々しくほほえむひかるの笑顔を見ると、なんだか心が軽くなった。
「なんだか次は、原稿通るような気がします」
真由美はそう言って、小説を書き直すべくしのみや食堂を早足で去っていった。