
「たとえば?」
振り向くと、そこには小学生の時の私がいた。赤いランドセルを背負って、あのときお気に入りだった服を着て、祖母が作ってくれた手提げかばんを持っている。みんなはキャラクターもので可愛いいものを持っていたのに私だけ地味な花柄で嫌だったことを思い出す。
「たとえばどんなこと?」
純粋な瞳で見つめてくる。この頃の私は、世界は夢と希望であふれていると信じて疑わなかった。
「いっぱいあるよ。四年生のときに隣のクラスの男の子が私のこと好きっていう噂があって、その子は私の友達のよっちゃんが好きだって知ってたのに、恥ずかしがって「あんな奴と付き合うとかあり得ないし!」って大きな声で言っちゃったの。そのあとその男の子いろんな子からいじられて可哀想だった。なんであんなこと言っちゃったんだろう……」
「そんなこと言っちゃったの?私はね、よっちゃんにこっそり「あの子はよっちゃんのことがすきなんだよ」って教えてあげたの。そうしたら恥ずかしそうにしてたけど嬉しそうだった」
「……どうしてそんなことがわかるの?」
「私はあなたとは違う選択をした私だから分かるんだよ」
私と、別の選択をした私……?
物語のような話だが、なぜか私は信じようと思った。
「二人はつきあえたの?」
「分かんない。教えてくれなかったの」
えへへと笑う幼い私は、遠くを見ていった。
「そっか。ひどいことしたな」
「そうだよ」
もしかしたらほかに後悔してることも別の選択をすることで救われていたのかもしれない。
「じゃあ、社会人のとき大きなプロジェクトをパアにしたことも?」
まだ新入社員だったのに会社の大きなプロジェクトグループの一員に入れたのが嬉しくて、飲み会のときに酔っていたからか内容をすべて話してしまったのだ。その後同じ居酒屋にいた他社の人間に盗まれてプロジェクトはなくなり、ついでに会社も居づらくなって辞めた。
「あったよね」
小学生の私は、大人になっていた。
黒いスーツをばっちり着こなして、ポニーテールも後れ毛がでないようにワックスで固められている。まさにキャリアウーマンだ。
「私は秘密は絶対守らなきゃと思ってそんなことしなかったな。そしたらまあプロジェクト大成功!いろんな人から頼りにされて、やりがいのある仕事ばかりでとっても楽しかった。」
「すごい……。私がいろんな人から頼りにされるなんて」
「でしょ?まあ婚期は逃しちゃったけど、その分色んな趣味始めたりして、仕事もプライベートもどっちも充実してる。」
そう語る私の目はきらきらと輝いていた。やはり選択を間違えていたらしい、後悔はどんどん大きくなっていく。
「そっちの私は結婚したの?」
「うん。したよ。でもすぐ離婚しちゃった」
仕事を辞めて実家に帰った私は、お見合いをした。顔は好みじゃなかったけど、誠実そうだし役所で働いていたからお金もそこそこ持っていたのでその人に決めた。しかし彼は周りがうるさいからという理由で結婚したらしく、男らしいところはおろか、夫らしくも父らしいところもみせてくれることなかった。しびれを切らした私は子供二人をつれて家を出て行った。「離婚はしないでくれ」とは言われたけど、それだけ。「これから頑張るから」とか自分を正そうとする姿勢は全く見えなかった。
「離婚したのね……。まあ、私も似たようなものだけど。」
「……」
次の私の姿に思わず絶句した。化粧をばっちりして、髪も綺麗に巻いていいて、胸元とふとももが露出された短いワンピース姿だった。まさか自分がこんな格好をしているなんて、近所のスーパーで六百円だったTシャツとスウェットパンツを着ている今の私からは想像できない。
「駆け落ちしたのよ」
絶句している私をよそに私が続けた。
「パート先に若い男の子が入らなかった?前髪が長くて目がよく見えなかった子」
「ああ…。」
声が小さくて店長によく怒られていた子だ。仕事も遅くてみんながいらいらしていたな……。
「えっ、あの子と?」
「ええ。私だって最初はなんだこのはっきりしない子はって思ったけど。ある日ね、突然言われたの。「髪がとっても綺麗ですね。俺の好みです」って。分かる?初めて女として見てくれたのよ。そして私を本当に愛してくれたの」
旦那はともかく、これまで私を女としてみてくれたこと男性なんて一度もなかった。私が単に避けていただけかもしれないけど、そんなことを言われたらと思うと体の奥が熱くなった。
「こ、子供たちは?」
「置いていったわ。彼とあの子たちは仲良くなれないし。でも流石に親として申し訳ないと思ってるわよ。寝ているあの子たちの頭を撫でて「がんばってね」って言って出て行ったわ」
「……親としてそういうことは」
「確かに親失格よ。でも私は、私のことをちゃんと見てくれる人を選んだの。それはいけないの?あなただって離婚して自分のことをちゃんと理解してくれる人を捜そうって思ったんじゃないのかしら」
何も言い返せなかった。
「それにあなた、子育て大変だったでしょ。ほんとは逃げたいと思ってたんじゃない?」
たしかに二人の子供は手を焼いていた。娘とは顔を合わせばすぐに喧嘩だし息子は地元の半グレ集団に入ってしまった。抜けるように注意したところ、逆上した息子に殴られ後ろにあった棚に頭をぶつけて死んでしまったのだ。
「私も……そっちにすればよかったのかな……」
悔しくて涙が出てくる。今まで失敗ばかりで楽しいと思えたことがなかった。ほかの選択をした私たちはこんなに楽しそうなのに、私はなにをしていたんだろうか。
「いままでつらかったね。もう死んじゃったけど、これからは私たちと楽しく暮らしましょう」
キャリアウーマンの私がそっと肩を抱いてくれた。
「ここで……暮らせるの?天国とか、地獄とかはないの?」
「ないよ。それになにもない。でも私が三人もいるんだもん。絶対楽しいよ」
「……三人とも、死んでるの?」
ほかの三人は目を見合わせた後うなづいた。
小学生の時の私はよっちゃんに悪ふざけで突き飛ばされたとき通りかかったトラックに轢かれ、キャリアウーマンの私は趣味の登山中足を滑らせ、駆け落ちした私は男の子と心中をしたらしい。
「なんだ……どの道私は長くは生きれなかったのね」
「そうよ。だからそんなに悲しまないで。これからは一緒に……」
「ママ!」
頭の上から娘の声がした。続いて息子の声もする。
「姉ちゃんどうしよう」
「あんたのせいだよ!あんたがよく分かんないグループに入っちゃうからママがこんなことになったんだよ!」
「そんな……そんなこと言ったって姉ちゃんだって喧嘩ばっかりしてただろ!人のこと言えんのかよ!」
「はあ?……そ、そんなの言われなくても分かってるよ……!」
また二人が喧嘩してる。小さい頃からよく喧嘩して、本当に懲りない子たちだ。ご近所さんに心配される前に仲直りさせなきゃ。
「どうしたの?」
「え?子供たちが……」
腕に鋭い痛みが走った。
「そっちに行ったらだめよ」
三人の私が腕をつかんでいる。
「あなたは死んでるんだから、今更生きている人間に同情しても無駄なの」
「でも……」
私は三人から離れようとしたが、腕の痛みはさらに増していく。でも、なぜ死んでいるのに痛いと思うんだろう…。
「もしかして私、まだ生きてる?」
地面が割れるような音がして私たちが姿を変えていく。雨が降る直前の入道雲のように黒く不気味な形。急いで逃げないといけないのに、頭では走っているのになぜか足はゆっくりしか歩けない。
「ナぜあなたが生きてイるノ」
「わタしたチは正しいセんたくヲしたのに…」
「なぜすべテ間違えたあナたが生きてイルの…」
「タダしいセンタくをしたのに、死んでしまッタラ意味がナイジャない…!」
脳裏に三人の亡くなったあとの様子が浮かんでくる。
よっちゃんに自分から飛び込んだと言われ、仕事に貢献したのに葬式には誰も来てくれず、心中した相手は生き残っていてほかの女と仲良くなっている。
「ヒドイでしょうウ…」
「イッショニここにいまショう」
あたりは真っ暗になっている。遠くの方に取っ組み合い始めた子供たちが見える。
「生キテイテもメンドウよ」
「コッチはタノシいヨ」
「わ、私は……!」
—————
目がさめたとき、私は生きてるんだなと思った。
白い天井と薄汚れた壁、窓の外には緑色の葉が風にそよいでいる。
「ママ!」
「ママ……」
次いで娘と息子の顔が見える。二人とも涙で顔がぐしゃぐしゃになっている。
「人殺しがママとか言うな!」
「うるせえ!」
「ちょっと静かにして」
頭をぶつけたところがガンガンと痛む。娘が手をつないでくれた。しわ一つない綺麗な手だ。息子は遠くに立ったままで、小さな声でごめんなさいと謝ってきた。旦那は……当たり前だけどいないみたい。
「聞こえませんけど」
「おまえには言ってない」
「いちいち喧嘩しない。おいで」
息子とも手をつなぐ。知らない間に大きくなっていて、大人になっていることを実感する。
「もっと怒った方がいいよ。ママ死にかけたんだよ」
「そうなんだけど、さっきめちゃくちゃ怖い夢見たからどうでもよくなっちゃった。でもあのグループには抜けなさいね」
「……うん」
「え、だからママの手なんか湿ってんの」
娘はぱっと手を離すとつないでいた手を息子になすりつけた。また取っ組み合いの喧嘩が始まろうとしている。
「やめてよもう!」
ずきずきと痛む頭の奥で「許さない…」という声が聞こえた。たとえこれまでの選択が間違っていたとしても、私は精一杯生きてやる。
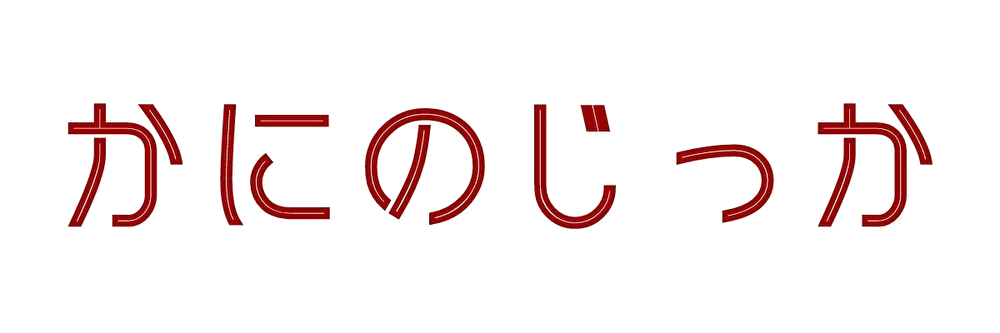
※コメントは最大500文字、5回まで送信できます