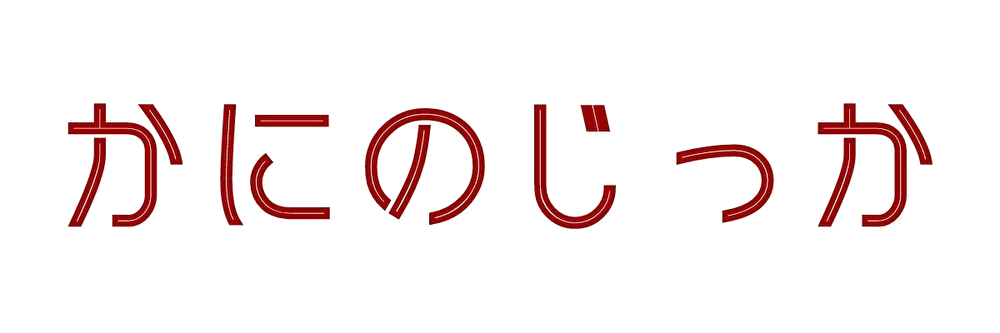三食丼
平日昼過ぎのファミレス。おしゃべりに花を咲かせる主婦や授業をサボっている学生たちが穏やかな時間を過ごしている。そんな中、梶田真由美はおびえたような顔つきで目を伏せていた。
真向かいに座っているスーツの男は真顔でノートパソコンの画面を見ていたが、やがて顔をあげ、にこやかに真由美に声をかけた。
「アイデアはいいと思います。このままだとありきたりすぎるので、もっと大きく変えていきましょう!ここからは本気で書いて、絶対に本にしましょうね先生!」
出版編集者である男の表情は明るいが、真由美の顔はさらに暗くなった。
かなり本気で書いたのに……。
これでもダメだったなんて。
真由美は、出版社が主催する新人小説大賞で審査員特別賞を受賞した。……十五年前に。それから今日まで、新作は発表されていない。
決してサボっていた訳ではない。これまで何度も小説を書いてきたが、どれも書籍になるまでには至らなかった。
原因は、ありきたりな話しかかけないことだった。一生懸命取材して書いても、面白い話が書けるセミナーに参加してみても、どこかでみたような、盛り上がりに欠ける話ばかり。思えば審査員特別賞を受賞した作品も、どこにでもいる普通の会社員同士の、普通の恋愛物語で、作品自体に新鮮さはなかった。「話は普通だが描写が独特」が、受賞理由だった。
賞をとって、その後なんの成績も出せていないのは真由美だけ。一緒に受賞した人たちも、あとから受賞した人たちも、大ヒットまではいかないまでも、着実に成果を上げている。その姿を見る度に、自分の至らなさに腹が立つ。そして自分の才能の無さに悲しくなる。
さすがに小説家一本では生きていけないので、一般企業で働く傍ら、隙間時間をみつけては小説を書く日々。最近は昇進して仕事量が増えたため、どちらが本業かわからなくなっている。
もういいかげん諦めたほうがいいかもしれない。
「この先の展開悩まれてます?」
神妙な面持ちの真由美を気遣い、もう八人目になる担当編集者が声をかけた。
「はい……」
「なんかね、小説家しか入れない食堂って言うのがあって、悩みを聞いてくれるらしいですよ。そこに行った人はみんなブレイクするって噂なんですけど、行ってみます?」
真由美は小さくうなづいた。まだもう少しだけ、あがいてみたい。
その食堂は富裕層向けの住宅街の中にある。
女将が愛人である大文豪に建てさせた家で、一人で切り盛りしているらしい。担当編集者から聞いた話を思い出しながら住宅街のなかを歩く。先鋭的な見た目の家たちが、うちが一番だといわんばかりに建ち並んでいる。
こんなところに家を建てさせたということは、相当高飛車なのかもしれない。
「これ小説って言わないから。もうちょっとお勉強してからうちに来てくれる?」
真っ赤な口紅のいわくありそうな女将から、とげのある言葉を言われたら……。そんな妄想をが頭をよぎり、足を重くする。
最寄りのバス停から歩いて十分。細くて小さな家があった。のれんも看板もない、普通の家。これが小説家しか入れないという、しのみや食堂らしい。
大文豪に作らせたにしては、いささか小さすぎる気がする。愛人だからこそ、あえてこのサイズ?でもなんでここに?謎が増えるばかりだ。
先ほど頭に浮かんだ怖い女将と相まって、恐怖でなかなかチャイムを押すことができない。でも、ここで引き下がるわけにはいかない。静かな住宅街を不審者のようにうろちょろするしていると、玄関の扉が開いた。
とても綺麗な女将さんだった。
黒くて長いさらさらの髪をひとつに束ねた細い体躯は、上品な素材の服と、落ち着いた色のエプロンがよく似合う。それに、黒縁眼鏡の奥で光る黄色い瞳は吸い込まれそうなほど綺麗だ。
「梶田様ですね。お待ちしておりました」
女将は丁寧な口調で真由美を迎えた。透き通るようなバリトンボイスは、もはや男性のよう、というか完全に男性のそれだった。
「男の人…?」
「……はい」
思い描いていた怖い女将は、完全にいなくなった。
しのみや食堂の中は、昼でも夜みたいに暗い。通ってきた廊下はもちろん、通されたリビングも生を感じられないほど暗くて静かだ。リビングの南側の小さな庭に木が一本植えられていたが、周りの高級住宅たちの影になって、光が届かず枯れていた。
それにこの家には装飾品が一つもない。あるのは食事に使う小さなテーブルと対のイス。テーブルの上を小さく照らすライトしかない。訪れた小説家のサインやメニュー表はおろか、時計すらない。殺風景を通り越して不気味だ。一度入ったら二度と出られない、そんな恐ろしい家なのかもしれない。捕まえた小説家たちを監禁して身の毛もよだつような恐ろしい惨劇が繰り広げられるのでは……。
あの、と声をかけられて我に帰る。目の前のひかるが首を傾げている。
「お代の小説を……」
「あっ、すいません」
先ほど編集者に見せた小説のデータを渡す。少し触れた手は、あたたかくて、男の人らしい骨ばった手だった。
「それではできあがるまで少々お待ちください」
ひかるはお辞儀をすると、そそくさと、となりの部屋に入ってしまった。あんなにあたたかい手の人が、そんな怖いことをするだろうか。不気味さは若干残るものの、この食堂の想像はほとんどなくなっていた。
真由美は頼んだのは、三食丼。
鶏そぼろと、鮭のほぐし身と炒り卵の三色。野菜嫌いな真由美のために、母がいつも作ってくれたおふくろの味。両親はいつも優しくて、小説家になったときも泣いて喜んでくれた。あれから15年経った今でも新作を待ち続けてくれている。そんな両親のためにもいいかげん本を出したい。
真由美はいつも持ち歩いているノートを開くと、次の新作となるはずの小説を書き始めた。
ひかるがお盆を持ってリビングに来た。
お盆に頼んだ三食丼ときんぴらごぼう、味噌汁が載せられていた。机に置かれると、ライトがほんのりと料理たちを照らす。腹が減っては戦はできないというし、まずは腹ごしらえだ。
箸で炒り卵をすくって食べる。卵、鮭、鶏そぼろの順で一口ずつ食べてから全部まとめて食べる、というのが小さい頃からのルールだ。綺麗な黄色。ほんのり甘くて、優しい味がする。次は鮭。こちらも綺麗なピンク色。塩気がよく効いている。最後に鶏そぼろを一口。醤油とだしの味が染みて美味しい。全部まとめて食べる。お互いが味を引き立たせていて、箸が止まらない。きんぴらごぼうはシャキシャキとした歯ごたえで、柔らかいだけの三食丼の良いアクセントになる。味噌汁の具はとうふとわかめの王道コンビだ。当たり前のことだけど、インスタントとは比べ物にならないくらい味が深い。
「はあ……」
味噌汁を飲むと、声が出てしまうのはなんでだろう。あたたかい汁がのどと胃を包み込んでいく。
どれもとても美味しい。母とは比べ物にならないくらい。なのに、思い出すのは母や父との思い出ばかりだ。あの時はこんな大人になるなんて少しも思わなかったのに。
おいしかった。ちょっといいところの定食屋さんでも、こんなおいしいものは食べられないくらいだ。真由美は、付いてきたお手拭きでテーブルを綺麗に拭くと、さきほどのノートを取りだしては、悩みを聞いてくれる時まで静かに待った。
二十分まっても悩みを聞いてくれる気配がない。来店時に渡した小説を読んでから始まるのだろうか。しかし書いてきた小説は十分ほどで読み終わる短編。皿洗いの音は聞こえない。まさか、本当に恐ろしいことが……?
真由美は考えるよりも先に動いた。台所の扉を開けると、あろうことか当の店主はのんびりプリンを食べていた。
「えっ!あ、すみません……何かありましたか?」
料理に文句があると思っているのか、手を止めて申し訳なさげに眉を下げている。
「あっ、いや、悩みを聞いてもらいたいんですけど……。悩みを聞いてくれるんですよね?ここって……」
「そんなサービスはありませんが……。聞くだけでも大丈夫なら聞きましょうか」
なに言っているんだこいつはという顔をされてしまった。これも嘘じゃない!次会ったらあのへらへらした編集者をぶん殴ってやろうと決心した。
皿洗いを終えたひかると、テーブルを挟んで向かい合って座る。テーブルには、お詫びのプリンが出されている。真由美はありきたりな話しか書けないこと、どうにかして本を出したいことを話した。より近くでみるひかるの顔は、モデルのように整っていて、人形のようにどこか可愛らしさがある。見る度に、女の人のように見えてしまう。
ひかるは静かにうなずきながら話を聞いてくれて、ゆっくりと口をひらいた。
「僕はありきたりな話好きですけどねえ」
……本当に話を聞くだけかもしれない。真由美のあきれた表情をみたひかるは、すみませんと小さな声で謝った。
「先生のお悩みは、ありきたりな話しか書けないことと、書いた小説をなんとかして出版したい、であってますか?」
「はい……」
「ありがとうございます。コミュニケーション能力がないので、素っ頓狂なことを言いそうで……」
ぺこぺことお辞儀をするひかる。先ほどまでのミステリアスなオーラはほとんど消えている。何度も謝るところ、会社にいる新人の男の子を思い出す。
「小説投稿サイトにアップするのはどうでしょうか?」
「えっ」
素っ頓狂な答えに驚いた。名前は聞いたことあるけど、アマチュアの、小説家じゃない人が書くイメージがある。真由美は、確かに本は出ていないけどプロの小説家だと思っている。
「それか、ブログなどで作品を投稿するのどうでしょう。読んだ人がアドバイスをくれて、ありきたりじゃない話が書けるようになるかもしれませんよ。本を買ってくれるのは編集の人ではなく、読んでくれる人なので、そこからの意見を得られるのはいいと思いますけど……」
だんだん声が小さくなり、気まずそうに窓の方を向いている。素っ頓狂ではあるけど、そういわれてみれば、そういう気もしてきた。読者が読みたいとおもう本を書くのは大事だ。それができたら本になるかもしれない。
「それに、僕みたいにありきたりな話が好きな人から評判をもらって、出版社から声をかけられて本ができるかもしれませんよ」
「それって、今の出版社の人に失礼にならないかな……」
「あっ……。それは確認したほうがいいかもしれないですね。でも、先生の希望は本を出すことなので、今の場所に固執しなくてもいいかもしれませんね」
ひかるの回答はどれも素っ頓狂で、おもしろい。
そんな考え方があるなんて、自分の視野が狭さに驚いた。そういうやり方もありなんだ。
「す、すみません……。全然、アドバイスになってないと思うんですけど……」
「そんなことない!ありがとう」
お礼を言う真由美の顔は、付き物が落ちたかのように、さわやかな顔をしていた。
ほおばったプリンは、甘くて思わず笑顔がこぼれた。